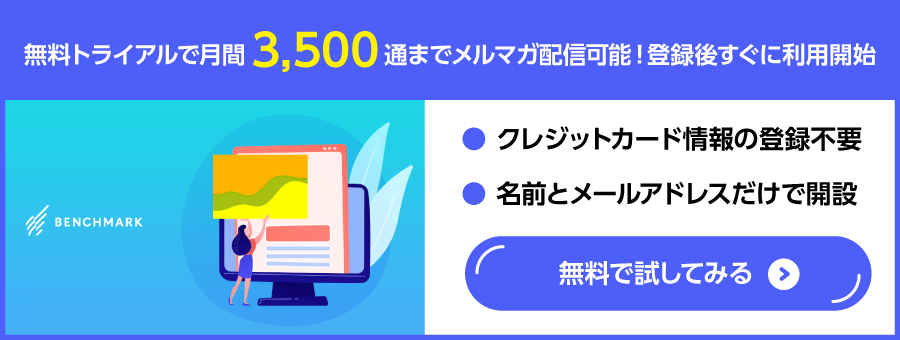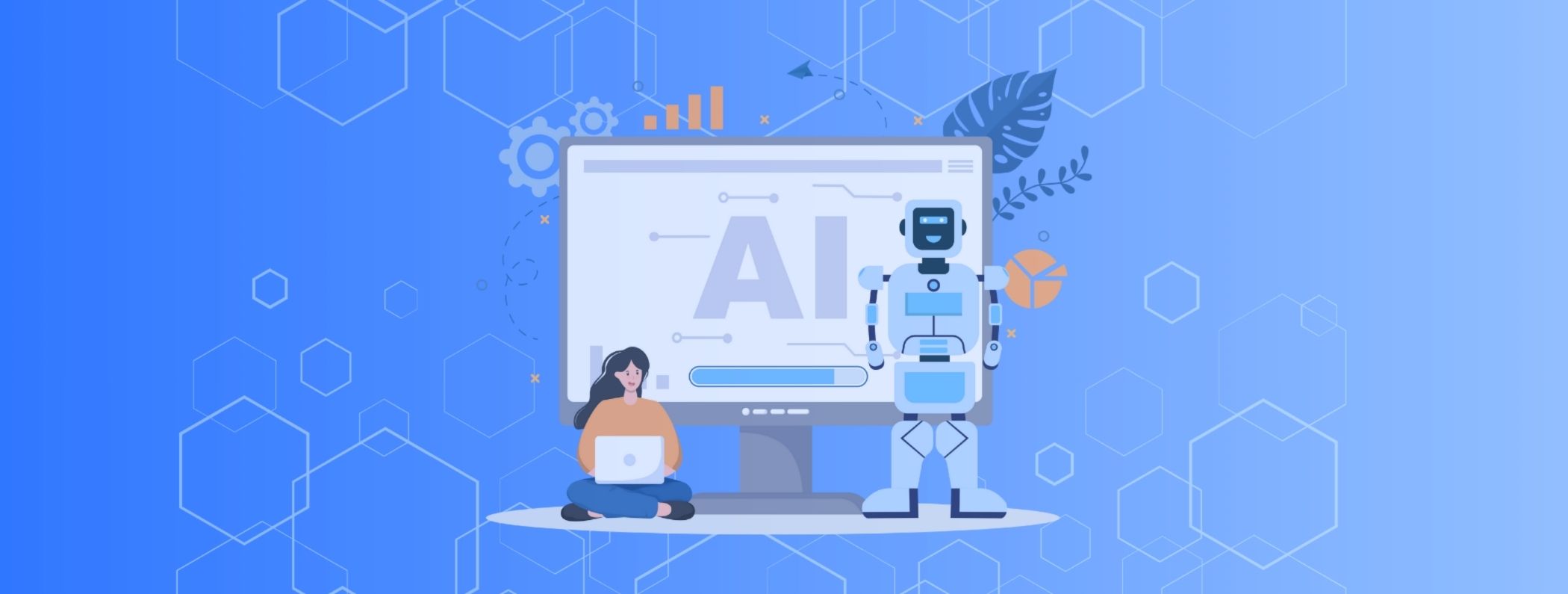この記事は「Why and How To Re-Engage Your Email Leads」を日本語に翻訳・編集したものです。
企業にとって、質の高いリードを獲得し、その関心を持続させるのは簡単ではありません。
多くの企業が全体の約60%が反応しない「非アクティブ(休眠)」な購読者を含むリストを運用しているとも言われています。ここでいう「非アクティブ」とは、直近のメールで開封・クリック・返信が見られない状態(一般的な目安は6ヶ月以上)を指します。
本記事では、なぜ離脱したのか(離脱原因) と どこで離脱しているのか(反応レベル) を見極め、読者の状態に応じて再アプローチ(リエンゲージメント)を設計する考え方をまとめます。むやみに同じ配信を続けて到達率が落ちるのを避け、関係を見直して成果につなげましょう。
目次
再エンゲージメントのメリットとは
ここで注目すべきなのは、対象となるのが「非アクティブ」とはいえまだリストに残っている購読者だという点です。配信停止には至っておらず、今もアプローチ可能な読者というわけです。
彼らはかつて自ら登録してくれた人たち──つまり、ブランドや情報に一定の関心を示した実績のある相手です。そのため、まったく関係のない相手への営業とは異なり、すでに一定の信頼関係があるといえます。この接点を活かし、できるだけ長く「メール購読者としてのつながり」を保ちましょう。
一般的な経験則として、配信性を守り、ISPからスパム判定されないために“反応のない購読者”を定期的にリストから削除する(リストクリーニング)ことが推奨されています。しかし、その前に一度「再アプローチ施策」を試してみる価値は十分にあります。
再アプローチは、削除に比べ費用対効果(ROI)が高く、うまくいけばリスト品質とコンバージョン率の双方を押し上げます。リストの健全性維持の観点でも有効な打ち手です。
購読者が離脱する原因ごとの施策
効果的な再アプローチには、離脱の背景把握が不可欠です。
よくある原因と対策は次のとおりです。
-
コンテンツの質・関連性の低下
→ 企画の原点回帰
読者にとって“本当に役立つ・今必要な”内容になっていないと、開封率は落ちてしまいます。心当たりがあれば、方針を見直し基本に回帰をしましょう。期待する反応を得るには、まずこちらが真摯に価値提供を続けることが前提です。 -
配信の頻度が高すぎる
→頻度の調整やまとめ配信
注意力と処理できる情報量には限界があります。“多すぎる”と感じられると、優先順位を下げられます。再アプローチの段階では、一時的に頻度を落とすのも有効です。 -
最初から関心が薄かった
→オプトイン種別の記録とセグメント方針見直し
魅力的すぎる無料特典をきっかけにした登録者は、“特典だけが目当て”という層を多く含む場合があります。せっかくならば、関心が高い層の育成に力を注ぐほうが効果的です。登録元(オプトインの種類)を記録することで、将来的に、本来の購読目的からずれた関心の低いグループに多くのリソースを投入してしまうリスクを回避することができます。 -
期待との不一致(約束未達)
→ 件名と中身の整合を徹底する
誇大な件名がつけられた非常に便利そうに見えるコンテンツの中身が、実際にはただのサービス紹介や宣伝コンテンツだった場合、信頼は損なわれ、購読解除に直結してしまいます。期待値設定と実体の整合を徹底しましょう。
反応レベルの見極め
「非アクティブ」といっても深刻度はさまざまです。どのタッチポイントで離れているかを把握し、適切にグルーピングして対策を変えましょう。
- L1:アクティブだがメールには無反応
メールは見ないが、Webや実店舗では行動している層。比較的再活性化しやすく、関心領域に沿った提案でメール接点も回復が見込めます。 - L2:ほぼ非アクティブ
メールも他チャネルも行動が乏しい層。再起動には時間と明確な価値訴求が必要です。 - L3:関与ゼロに近い読者
購入履歴も行動もなく、登録以外の接点が皆無な層。効果は限定的で、リソース配分の観点からも優先度は低いと判断すべきケースがあります。
反応レベルごとの再エンゲージメントの進め方
L1:他チャネルではアクティブだがメールには無反応
こうした購読者には、設定見直しや関心テーマの再選択を促す再アクティベーションメールを送りましょう。
反応がない理由として、これまでのメールがその人にとって十分にパーソナライズされていなかった、あるいはコンテンツに魅力や価値を感じてもらえていなかった可能性もあります。したがってメールの内容を見直し、購読者にとって本当に役立つ・興味を引くものになるよう改善することが重要です。
なお、再アプローチは一度きりで終わらせず、最低でも3回は接触を試みましょう。
L2:主要チャネルすべてにおいて非アクティブ
この場合は、これまで以上に踏み込んだ対応で、ブランドとしての「価値」をあらためて明確に伝え直すことが求められます。
特別オファーや限定キャンペーンのほか、「ご無沙汰しております。あらためてご縁を持たせていただければ幸いです。」のように、関係再構築の意思を率直に伝えるメッセージも有効です。
直近数ヶ月間のニュースや特集記事、売上実績、話題となったトピックなどを効果的に紹介することで、ブランドの魅力や信頼性を強調することができます。さらに実際の顧客からの声や体験談といったお客様のリアルな評価を盛り込むことで、ブランドの価値をより具体的に伝えることができ、メッセージ全体に説得力と温かみが加わります。このような要素を活用することで、購読者の関心を再び引き寄せるきっかけを作ることができるでしょう。
一方で、一度も購入がなく、メール/Web/SNSのいずれにも行動が見られないアドレスは、思い切ってリストから除外する選択も必要です。限られたリソースは、関心の高い層に集中投下したほうが成果が出ます。
関係性を途切れさせないために
購読者リストを見直していると、いわゆる「反応のない購読者」が一定数存在することに気づくかもしれません。そうした購読者はそのままにしたり、削除するのではなく、まずは再エンゲージメントの機会を持つことが大切です。
重要なことは、再エンゲージメントの目的は興味を失った購読者に対していきなり最初のメールで購入してもらうことではないということです。また、そのメール1通を開封してもらうことだけがゴールでもありません。
本当に目指すべきなのはその購読者があなたとのやり取りを再び始め、信頼関係を築いたうえで最終的に定期的に購入してくれるようになることです。そのために時間をかけて丁寧に関係性を再構築することは、とても価値のある取り組みです。
焦らず段階的にアプローチすることで、信頼と関心を取り戻し長期的な成果につなげていきましょう。
関連記事